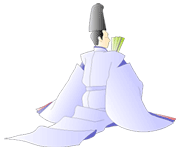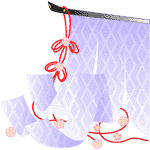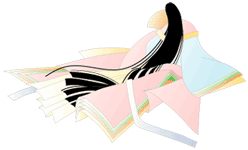[ 一 誕生 ]
権大納言清成卿は、目の前に座すおのが息子の姿に惚れぼれと見入った。
すっきりと伸びた背筋。子どもの証であったみずら髪もつい先ほど解かれ、今は華奢な首筋があらわになっている。その頭上に頂くのは、真新しい冠。
「父上。母上」
装いをあらためた息子は、居住まいを正し、両親の前で頭を垂れた。
「このたびの儀をもちまして、私も成人男子のうちに入るを許されました。若輩者ではございますが、何とぞ、よろしうお願い申し上げまする」
「うむ」
完爾と笑み、権大納言は手の内の扇を鳴らす。
その音を聞いて、廂の間に控えていた女房がひとり、心得顔に膝行してくる。
黒塗りの高坏のうえに乗せられているのは、祝い酒。
「これより先は無礼講といえど、皆、そなたの元服を祝いにおいでくださった方々。心して御礼など申し上げよ」
「はい」
「先んじて、まずはこの父から祝い申し上げる。さ、近う」
衣擦れの音ともに、息子は父の前にかしこまる。
その盃になみなみと酒を注ぐ。権大納言の盃には、傍らに控えた西の奥方が。
「ありがたくも、主上よりはすでに五位を賜った。万事心得て、誠心誠意お仕え申し上げよ。まずは、めでたや」
「ありがとう存じます」
共に盃を掲げて、一息に干した。
「まこと、噂に違わぬ御器量でいらっしゃることよ」
「おお。権大納言様も、さぞや鼻が高かろう」
「主上も、太夫の君の参内をいまや遅しとお待ちかねでいらっしゃると聞き及んでおりますぞ。この秋には、まず間違いなく昇進なさいましょうな」
加冠・給禄・叙位と滞りなく元服の儀は終わり、今や権大納言邸では盛大な祝宴が催されていた。
祝いと称した、新たな殿上人の品定めに集った方々は、今し方、目にした若君の噂話に余念がない。
噂だけには聞いていた権大納言家ご自慢の若君を、今宵初めて目にした者も少なくなかった。はたして、戌の刻を迎えて姿を見せた若君は、姫と見紛うほどの愛らしさ。なるほど、これでは父大殿が童姿を惜しんだのも無理はないと誰しも思ったほどだ。
しかしそののち髪を切り、髻を結い、冠を頂いた時には、誰もが感嘆の声を洩らすほどの世にも美々しい公達がそこに居た。
「──そういえば、こちらの妹御は、兄君に生き写しであられるとか」
誰ともなくそう言い出したのは、当然であったかも知れない。
「おお。兄君があれだけの御器量。さぞやお美しかろう」
「お家柄も申し分なく。……こうと言っては何ですが、右大臣家の御方は、皇后にはおなりになれぬ。その点、こちらは申し分ないお血筋でいらっしゃる」
「しっ! 滅多なことを申されるな。大殿のお耳に届いては、一大事ぞ」
にわかに声をひそめたのも無理はない。今夜の儀式で加冠の役を勤めた当の右大臣が、目と鼻の先に座しているのである。
(かしましいことよの)
ざわざわと興奮さめやらぬ様子で盃を交わす人々の間にあって、右大臣は皮肉げにそうひとりごちた。
右大臣ほどの上級貴族となると、我が家の繁栄は入内した娘がどれだけ帝の寵愛を受けられるか否か、その一点に収束する。
寵愛を受け、男御子をお産み参らせ、なおかつその皇子が次代の帝となったなれば、お家は安泰。しかし、ここにひとつの問題がある。
右大臣家は、摂関家ではない。すでに一の姫が入内し、女御として遇されてはいるものの、それが后の位にのぼることは決してないのである。
(ましてや──この家には、絶好の后候補がいる)
関白左大臣家の血を引く、由緒正しい妙齢の姫君。右大臣が喉から手を出しても欲しいその存在が、この家には居るのだ。
父大臣によれば、極度の人見知りで、初めて会う女房にすら、ろくに顔を見せないと言う。しかし、そんなものは詭弁に過ぎないだろう。本来なら早々に済ませていておかしくない裳着を遅すぎるほどに遅くし、世の人の耳目を集めた。加えてあの若君の妹である。若君の出仕に伴い、その妹姫の噂も宮廷中を駆けめぐるだろう。
嫉妬と羨望にきりと唇を引き結んだ右大臣だったが、やがて衣をあらためて再び姿を見せた今宵の主役の姿に、顔つきをあらためた。
まこと男にしておくのが惜しいほどの美形だった。
さらさらとした衣擦れの音こそすれ、無粋な物音は一切たてない。流れるような身のこなしだった。
結い上げたばかりの髪はもう冠の下に隠れてあまり見えないが、その手触りの艶やかだったこと。うなじから立ちのぼる香気は、この日のために念入りに焚きしめた秘香に違いなく、右大臣にしてからが思わず目を見張ったほどだ。
声もまだ若く、懸命に低く落ち着いたように話すようすが何とも微笑ましい。この名門の出にして、この器量。
(予想以上の逸材であった。これを逃す手はない)
(──いずれは、是非とも我が家の婿に)
右大臣の熱望は、やがて世の人の知るところとなる。
そもそも、権大納言卿は都でも有数の名門の出だ。父は関白左大臣、その直系であることは、将来を確約されたも同様。
家柄の申し分なさは言うまでもなく、本人の器量も相当のものだった。
容姿はもちろん、学問の造詣の深さは学者を唸らせ、人当たりも良く、帝の御覚えも上々。世の人々がうらやましく思うのもまったく当然だった。
そんな彼が、ある女性の許に通い始めたと知ったとき、色好みで知られたある貴族は首を傾げたものだ。
曰く「彼の御方も、人の子であったか」と。
その女性は源宰相と言う方の姫君で、名は寧子。親子ともども、家柄は悪くないもののどこかおっとりした、言うなれば出世街道から外れないながらも傍道を歩いているような人々で、容貌もとりたてて良いとも噂を聞かない。事実、姫の器量は十人並みであったらしい。
権大納言ほどの御方が、とんだ見誤りをしたものよ──と、世の人は噂したという。
だが、元来お人好しだった権大納言は、寧子姫の許から足を遠ざけることはなかった。なにしろ初めて通った女性である。いくら顔だちが期待はずれだったからといって、それだけで離れるのはどうかと思った。それに、人柄は好もしい女性であったので、その後も変わらず通い続けた。
ただし、代わりに別の女性に期待をかけた。藤中納言の娘、隆子姫である。
ところが。これも、はずれだったのだ。
人柄は良かった。それ以上に教養が申し分なかった。男顔負けの学識であり、才であったのだ。ことに手蹟の見事さは、まさに一見の価値があった。
しかし容貌はといえば、やはり十人並みだったのだ。
落胆した権大納言は、それ以上の女性を望もうとはせず、ただふたりだけの許に通い続けた。
そうこうするうちに、先の寧子姫が、男の子を産んだ。
「──殿、御覧くださいまし。何と可愛らしい御子でしょう」
取り上げられた赤子とようやく対面かない、その小さな命を抱かせてもらった時、権大納言は感動に胸をふるわせた。
親の贔屓目というには、それはあまりに可愛らしい子どもだったのだ。
「おお」
一言唸ったきり沈黙している夫を、まだ床に伏したままの北の方は心配そうに見上げた。貴族の姫、それも大貴族の妻となれば、まず娘を産まなければお話にならない。息子を何人産んだところで、家を継げるのはひとりきり。しかし、娘は帝のもとに入内でき、家の繁栄の要になるのだから。
「殿?」
「……なんと、可愛らしい」
やがて感動もあらわにもらされた言葉に、寧子姫は安堵の吐息をもらした。
「よくやった、寧子。よくやったな」
ねぎらいの言葉ともに笑みくずれた権大納言に、やきもきしていた周囲の女房達もようやく笑顔になる。
それからふた月を経ずして、今度は隆子姫の許に女の子が産まれた。
「殿。どうぞ、抱いてあげてくださいまし」
誇らしげな隆子姫の腕から、権大納言はこわごわ念願の娘を抱き上げた。
とたん、小姫は火のついたように泣き出した。
「まあまあ、姫。父君ですよ」
慌てたように乳母がなだめにかかったが、小姫は一向に泣きやまない。
途方にくれた権大納言は、ためしに軽く小姫を揺すり上げた。
「ほうれ、泣きやめ。父御じゃぞ」
そんなもので泣きやむなら苦労はしない──と隆子姫と乳母が思ったとき、ぴたりと小姫が泣きやんだ。
「おお」
権大納言は喜色満面で、あらためて小姫の顔をのぞき込んだ。
つぶらな瞳が、目尻に涙を残したままで、じっと権大納言を見上げてくるそのようすは、まことに愛らしい。
しかし、それ以上に、権大納言は驚きに目を見張った。
「なんと、まあ」
「殿?」
不審げに声を掛けてくる妻に、権大納言は、笑いかけた。
「ああ、いや。あまりにそっくりなのでな、驚いた」
「そっくりと、申されますと」
「赤子は、どれでも同じように見えるものか。何とも、よく似ておる」
そう聞いて、思い当たった隆子姫は目を丸くした。
「あちらの若君と、わたくしの姫が、そんなに似ておりますか」
「うむ。不思議なこともあるものよ」
「まあ」
隆子姫も、あらためて我が子の顔をのぞき込んだ。
今は機嫌よさげに父親の腕におさまっている小姫と、同じ顔がもうひとつあろうとは。
「赤子のうちは、そう言うこともありましょうか。けれど、育つうちに顔立ちも変わりましょう。何と言っても男と女ですから」
「そうかも知れぬ。しかし、今はうっかり取り違えそうで何やらこわいくらいだ」
そうしてつくづくと姫の顔を眺める夫に、隆子姫は胸中複雑なまま笑んだ。
ふたりの妻のどちらもが、それほど容色に優れていないのがやはり不満だった権大納言は、妻たちとは似つかぬほど美しい子どもたちに夢中になった。通いの足は絶えることなく、むしろ繁くなり、子どもを間に挟んで夫婦仲はしごく円満。子はかすがいとはよく言ったものである。
しかし、やがてその御子たちがいずれ劣らぬ心痛の種になろうとは、さすがの権大納言にも予想し得ぬことだった。
戻 る 進 む
(C)copyright 2002 Hashiro All Right Reserved.