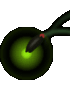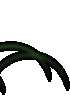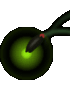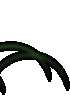[ 一 光明 ]
春を過ぎ、夏の終わりの頃になっても、絢貴と四の君の間に、元の穏やかな空気は戻るようすもなかった。
さすがにその頃になれば、家人も世の人々も、何かおかしいと気づき始める。
「子が出来たとなれば、もうすこし……何というか、見た目にもいっそう愛情深くなるものだと思うのだが」
絢貴の人柄をはばかって、はっきりと口にはしないが、誰しもがそう思ってしまうほどには、ふたりの仲は傍目にも冷え切っていたと言える。
「いったいどうしたことでしょう。あれほど仲の良いふたりでしたのに」
「絢貴どのは、今日もお渡りでないか……ふむ」
両親が、顔を見合わせてはため息をもらすようすを見聞きしている四の君こそは、いたたまれない。
何と言っても、右大臣家の姫。離縁されることはなかろうが、形ばかりの妻とされるのも耐え難い。しかし、その原因をつくったのは自分なのだと。
一方、その元凶である宰相中将は、こうした絢貴のようすを見て、ますます四の君への想いを深くした。
左衛門に四の君のようすをくわしくたずね、そのいじらしい姿に心悩ませ、
(こうなれば、世の良識も人目の見苦しさも構うものか。あのひとを盗み出して、誰も知らぬところに隠してしまおう)
思い詰めてはみるものの、そんなことがおいそれと出来るはずもなく。
毎日のように宮中で顔を合わせている絢貴は、やがて、そんな宰相中将を不審に思い始めた。
(いつも明るく人好きのするこのひとが、ひどく物思いし始めたのは、ちょうど桜の頃合いだったが……もしや)
そう思い始めてから、ますます注意深く、それとなくようすを見、さらに疑いを深めていった。
(もとより、このひとほど四の君に想いを寄せていたひとも思い当たらない。しかし、本当にこの男だったら、私のことをいったいどう思っているやら)
宮中ではもっとも気心が知れた相手、との自負があるだけに恥ずかしくもあり、くやしくもある。けれど、本人にそれとたずねるわけにもいくまい。
(何と憂き世かな──。父母の嘆きを思って、いつまでも俗世に留まっていた私の、なんと愚かなことよ)
今こそ出家遁世して、仏道修行に励みたい──そんな思いがいや増していたある日のこと、寄っていた実家で、興味深い話を耳にした。
先頃より、吉野山に、先帝の三の御子がおわすという。
万事に優れていらっしゃる御方で、世の人の為すこと、各種の学問、陰陽道、天文学、夢占から人相見に至るまで、なべて道を極めた才人であられるとか。
「そのような方の噂を聞いたことがあります。確か、ずいぶんと前に唐土に赴かれておいでではなかったかな」
絢貴がたずねると、
「はい。日の本にお戻りになられましてから、しばらくは都に落ち着かれておいででしたが、数年ほど前に御髪を下ろされ、吉野に居を定められたとか」
「ふむ」
「御本人に直接拝謁申し上げたことはございませんが、そのお住まい。まったく俗世からお離れになった聖人さまにふさわしく、水の流れ、庭の石の佇まいも、都ではまったく見慣れないふうでいて、心鎮まり、かつ心配りの行き届いた素晴らしいつくりでいらっしゃいます」
「ほう、そのような方がいらっしゃるのだな」
父君が感心したように仰るのに相づちを打ち、
「そのように高いご身分でありながら、自ら望んで山に籠もられるなど、御心もお姿も、平凡ではいらっしゃらない御方なのでしょうね」
軽く聞こえるよう受け答えしつつ、絢貴はその宮のことを深く心に刻んだ。
出家したいと漠然と思っていたが、具体的にどうしたいとは形になっていなかった。人も知らぬ谷の奥や、峰の上で庵を構えたいとは、言うは易く、行うは難い。
だが、吉野の宮の話を耳にして、にわかに目の前が開けた思いだった。
数日後、絢貴は話をしていた男をひそかに呼び寄せた。
顔見知りていどに知ってはいる、左大臣家に仕える下級の官吏だった。
呼び出されたことで男はひどく恐縮していたが、絢貴が「宮のことを聞かせて欲しい」と頼むと、どうにか緊張も解けたようすだ。
「あなたはどういったご縁で、宮のことを親しく知り申し上げたのかな」
「はい。伯父にあたる者が宮のお弟子でございまして、夜昼おそばを離れず、仏道修行に励んでおります。用があります折々、訪ね申し上げております」
「それは嬉しいことだ。実は、私は宮のお噂を聞いて以来、かねがね、お訪ね申し上げたいと思っていてね。継ぐ人も絶えてしまった琴の琴や、読み解くに苦労している書物のあちこちらをご質問したいと思っていたのだけれど、それほどきっぱりと俗世をお切り捨てになったお身の上でいらっしゃるからには、ご承知下さるまいと諦めていたのです。
よければ、宮にご意向を伺ってもらえぬだろうか。良いと仰ってくださるなら、ひそかに参上いたしたい」
その身分しては考えられないほど丁寧な物腰に、男はいたく感激したらしく、胸を張って承諾した。
「お任せ下さい。容易い御用にございます」
「ありがとう。では、早々にお訪ねしておくれ」
絢貴の願い通り、男はさっそく伯父の僧をたずねた。
「伯父上、実は」
吉野に着く早々に切り出せば、まあ落ち着けとなだめられた。
「ふむ。で、どなたと申したかな。左大臣家の若君。絢貴さま、か」
「はい。伯父上、ご存知なのですか」
「この草深い吉野にも、すぐれた御方の噂くらいは聞こえてくるよ」
「それならば、話が早い。噂通りに素晴らしい若君でいらっしゃいます。是非とも、お志を叶えて差し上げたいのですが」
「ふむ。──以前にも、しかるべきご身分の方がお出ましで、御口上をお伝えもしたのだが。宮さまは、まだ生きていたのだなどと噂されたくないと仰って、まったくお聞き入れなさらなくてな。ここ四、五年ばかりは、どなたも訪れなくなって久しい」
「では」
あからさまに肩を落とした男に、
「まあ、待て。どうお答えになられるかは分からぬが、ともかく宮さまに伺って参るゆえ。しばらくここで待っていなさい」
男をその場に待たせ、僧は宮のもとに向かった。
「宮さま。すこし、よろしいでしょうか」
「どうぞ」
お声を得てから御前に参ずると、文机を脇に押しやった宮が振り返った。
「何ごとか、ありましたか」
「はい。実は、私の甥を使いに、さる方より御口上がありまして」
「おや。まだ私のことを覚えていらっしゃる方がおありですか」
興味をひかれたようすで、宮が先を促した。都嫌いの宮さまにしては珍しい、と僧は首をひねったものの、甥の伝言をそのままに奏上した。
「──いかがでしょう。お会いくださいますか」
しばし思案したのち、宮は穏やかに微笑んだ。
「あれほどの栄耀に包まれて、さぞ華やかな暮らしをしておいででしょうに。いかように私のことをお聞きになって、この深山に心を向けられたのでしょうね……」
やはり駄目かと僧がひとり頷いたとき、
「しかし、それもしかるべき縁がおありの方なのでしょう。嬉しいことです。このように鄙びたところでよろしければ、ぜひおいで下さるように、と」
「は」
思っていたのと正反対の答えを返されて、僧はわずかなあいだ固まった。
「どうしました?」
清々しいまでの笑顔を向けられて、僧はあわてて平伏した。
「いえ。確かに承りました」
御前を下がり、待ち構えていた甥に伝えると、男は飛び上がらんばかりに喜んだ。
「ありがとうございます、伯父上。さぞやお喜びになられましょう」
「ふむ」
「何か?」
「ああ、いや。あまりにあっさりとご承諾なされたのでな。……何か、心に響くところがおありだったのだろう。よい、気にするな」
「それでは、伯父上」
「うむ」
喜び勇んで帰った男は、さっそく、宮が快諾されたことを絢貴に伝えた。
絢貴がこのうえない喜びに包まれたのは、言うまでもない。


(C)copyright 2004 Hashiro All Right Reserved.